
ウチの商売は家とお店(事務所)が一緒だから、電気代とかもうごっちゃなんだよね。
どうやって分ければいいのかな?
こういった問題は、個人事業者にとっては当然ぶちあたる疑問になると思います。
法人であれば、その辺りはきっちり分けて計算しないといけません。しかし、個人事業者の場合、事業用と家庭用が必ずしもきっちり分かれているとは限らない、という方が大方だと思います。
今回は、こういった問題について以下のとおり解説していきます。
〇家事関連費とは
〇家事関連費の記帳方法
家事関連費とは
家事関連費とは、業務用の部分と家事用部分からなる費用のことを言います。例えば自宅兼事務所の水道光熱費、業務用家庭用兼務の自動車の燃料費、車検代などです。
事業主やその家族の生活費、住宅費などの家事費(家庭用の費用)は、必要経費として計上できません。
青色申告者は、業務の遂行上直接必要であることが、取引記録や帳簿などにより明らかにできる金額を、業務用部分の費用として必要経費に計上することができます。
家事関連費の記帳方法
家事関連費を計上するためには、その前に必要経費と家事費用を合理的に区分する必要があります。
合理的区分とは、業務に使用する面積、時間、量、頻度(自動車であれば距離など)等を総合的に勘案して基準を一つ定めることを言います。もちろんですが、その基準は自分一人よがりで勝手に決めたものではいけません。あくまで、世間一般から見て妥当である、と考えられるような明確かつ納得させられる基準でなければなりません。そして、その基準で割り出した割合で按分計算します。
記帳方法として、①家事関連費の支出のその都度家事費部分を区分する ②決算の際に一括して1年分の家事費部分を区分する のいずれかの方法になります。
典型的な例を表にまとめてみます。
| 家事関連費の例 | 按分基準の例 |
| 店舗併用住宅の賃貸料、修繕費、減価償却費、固定資産税など(購入した場合の借入金利息を含む) | 〇土地や建物に関するものは使用する面積など |
| 業務家事共用の自動車のガソリン代、整備費用、税・保険料、カーローンの支払利息、リース代など | 〇自動車や機械に関するものは、使用する時間、頻度など |
| 電気料金、電話料金、ガス料金、水道料金、灯油代など | 〇使用する時間、量、頻度など |
これでもやっぱり、「基準っていったって、どうすればいいのかわからないよ」という場合もあるかもしれません。
一定の基準として、自分が税務署の職員や税理士に「この基準はどういったことに基づいて計算しているのか」と聞かれたときに、ある程度「ああ、なるほど」と納得させられるような基準で分けてみるようにしてください。こういった時に「よくわからないけどやってみた」と言ってしまうのが一番よくありません。
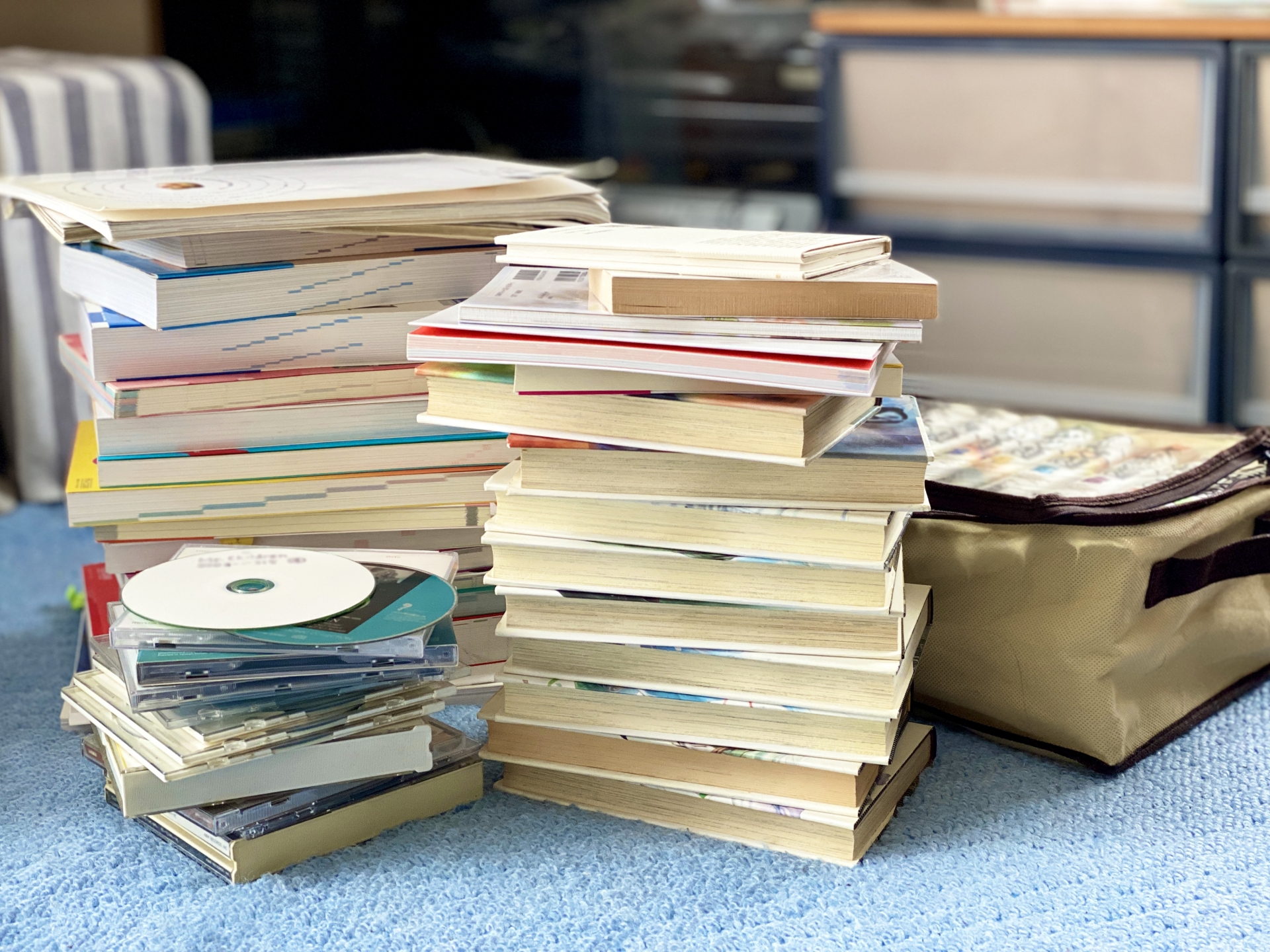

コメント